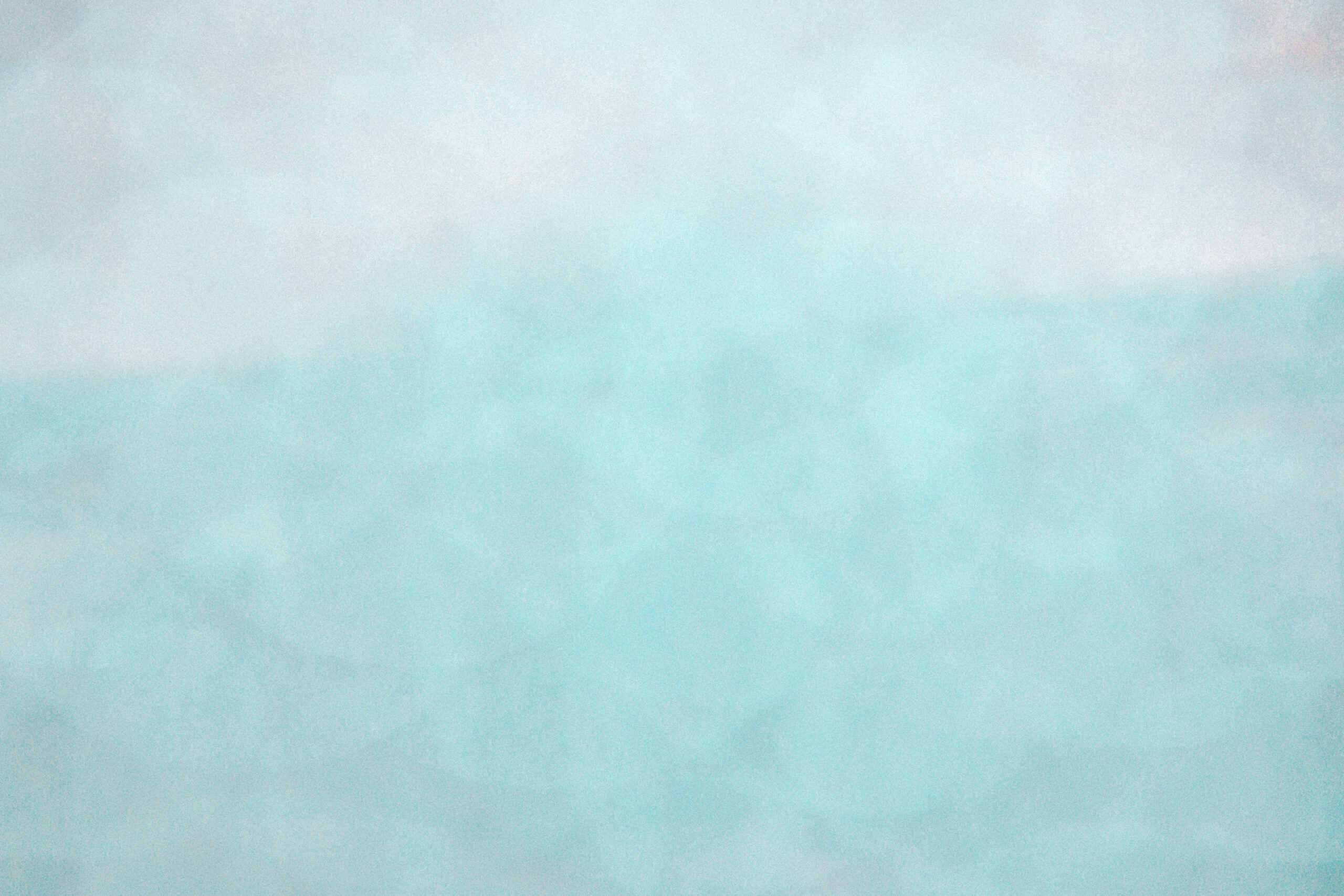とある国立研究所様から、ホームページリニューアルにあたってのご相談がありました(一部伏字)。
国立●●●●●●研究所の●●●と申します。
当研究所では、●●●●●●●関連の情報ページを作成し、以下URLで公開しております。
記事が新しい順に表示しているのですが、記事の種類が多岐にわたり(●●●●関連記事、●●●●●記事、●●●●●向けガイダンス、●●●●●●●な解説記事、研究情報、その他お知らせ等)、数も多くなってきたことから、目的の記事を探しにくいという指摘をよく受けます。●●●●●●ページに限らず全体としてもです。このような作りになっている背景としては、記事を作成し発出する部署が複数にわたること、また、当所にはホームページのコンテンツ管理や掲載業務を行う特定の部署が存在しません。そのため、HTMLなどの知識のない各部の研究員が掲載作業を行うことができて、かつ、(各部が発出する記事を取りまとめる部署が存在しないことから、)CMS等により投稿した記事が機械的に適切な場所に表示されるよう制御されている必要があります。そのため、新しい順に表示するなどのシンプルなものになっています。
このような特殊な事情があり、導入しているCMSによる技術的な制約も大きいのですが、なんとかもう少しわかりやすくコンテンツを配置できないものかと思案しております。
記事の種類(上記のような)による分類、ターゲットによる分類、また、ニュース記事のような揮発性のものやある程度古くなっても参照可能な解説記事などの分け方もあると思いますが、このような多岐にわたる記事をどのように整理し、どのようにレイアウト/デザインすると見やすいかについて、ご相談させていただくことは可能でしょうか?
ホームページコンサルタント永友事務所では、「ホームページをわかりやすくする」という趣旨のご相談を多く承っています。
(参考)提供サービスの提示のしかた(並べ方)を変更したサービス業様
(参考)葬祭業様ホームページ改善支援
(参考)体験教室(入会説明会)時のプレゼンテーション内容についての助言
(参考)誰に対して言っているのか分からないホームページ
(参考)貸切・観光バス業様のホームページ掲載内容整理
むしろホームページコンサルティングのプロセスでは「わかりにくい情報を、わかりやすくする」ということは不可欠なため、「ホームページのわかりやすさ」についてのアドバイスを常に行っているような感じです。
この国立研究所様とのディスカッションでは、大きく以下のような点について協議、アドバイスをさせていただきました。
ペルソナの再設定(素人向け?玄人向け?)分かりにくいというのは主に誰(素人/玄人)か?
この研究所様には、まず「閲覧者としてどんなかたを対象と考えているのか」をお尋ねしました。その結果、概ね数種類の想定閲覧者(ターゲットユーザー)があることが分かりました。その中心はBtoBであり、その分野の方々が、公的な情報を求めて閲覧するものということでした。
そうなると、いわゆる「新着情報」以外にも、「よく閲覧されることが想定されるコンテンツ」への動線提示をすることが望ましいということをお伝えしました。
またその「新着情報」も、数年前の情報がずっとトップページの「新着情報」欄(のかなり下部)に載ったままであることも、ぱっと見の複雑感が出るので新着情報の数も制限することをお勧めしました。
グローバルメニューの見直し
グローバルメニューとは、全ページの目立つ位置(パソコンのブラウザで見た場合は、概ね最上部や左右の端)に出ている、メインメニューのことです。利用者の多くは、このグローバルメニューを頼りに他ページに移動していきます。
ここでは、グローバルメニューに載せなくても良いメニューや、かえって閲覧者を惑わせるようなメニューを削除することをご提案させていただきました。
似たようなラベリングの廃止
メニューの名称、付された文字のことをラベリングといいます。例えば「お知らせ」とか「会社概要」のような文字列のことです。
本件では、「似たようなラベリング」が混在することで閲覧者を惑わせていることが予見できましたので、そのラベリングを変更することをご提案させていただきました。
コンテンツに強弱をつける(メインではないものは思い切って削除するか存在感を低下させる)
本件では、例えば「アクセスの多い記事」というコンテンツがありました。これはよく考えると「ほとんどの一般閲覧者にとって無意味な情報」になります。せいぜい、ホームページ運営者様自身が「どんなページがよく見られているのか」がパッと見ですぐわかるという効果しかありません。
このようなコンテンツも含めて、このホームページは「様々なコンテンツがほとんど同列、同じトーンで」発出されていて、どこに重要情報が載っているかが極めてわかりにくいという雰囲気がありました。
「どこを見るべきか分からない」というのは閲覧者にとって非常にストレスになります。重要でないコンテンツは、削除するか控えめな場所に移動するかなど、力配分を見直すことをご提案させていただきました。
他にも、
■パンくずリストを設置する(居場所を明示する)
■画像(ボタン)を使う(単純に文字ばかりなので読みづらい)
■リンクではないところに下線を使わない
■「最新」という言葉の曖昧さ(いつの時点での「最新」?常に最新であればその明示を)
■スマホ対応にする
などについてご提案し、ディスカッションさせていただきました。
ホームページが「わかりにくい」という指摘を受けた。でも誰に相談すればよいか分からない…という場合に、永友事務所を思い出していただければと思います。
●多くなってしまったホームページ内容の整理をしたいというご用命が増えています。
●サービス業Web活用では「利用エピソードの描写」が最重要です。その意味とやりかたをご助言します。
自社ホームページを客観的に見直したい経営者様へ
貴社のホームページは、顧客に伝わる言葉、表現になっていますか?また、顧客に届きやすいツールを選択していますか?
ホームページコンサルタント永友事務所では、「お客様目線の表現術」「Web活用の全体の最適化」について店舗経営者様へのアドバイス実績が豊富です。
お仲間で集まっていただければ、講習会形式でのコンサルティングも可能です。「お客様目線のWeb発信について」とご連絡ください。